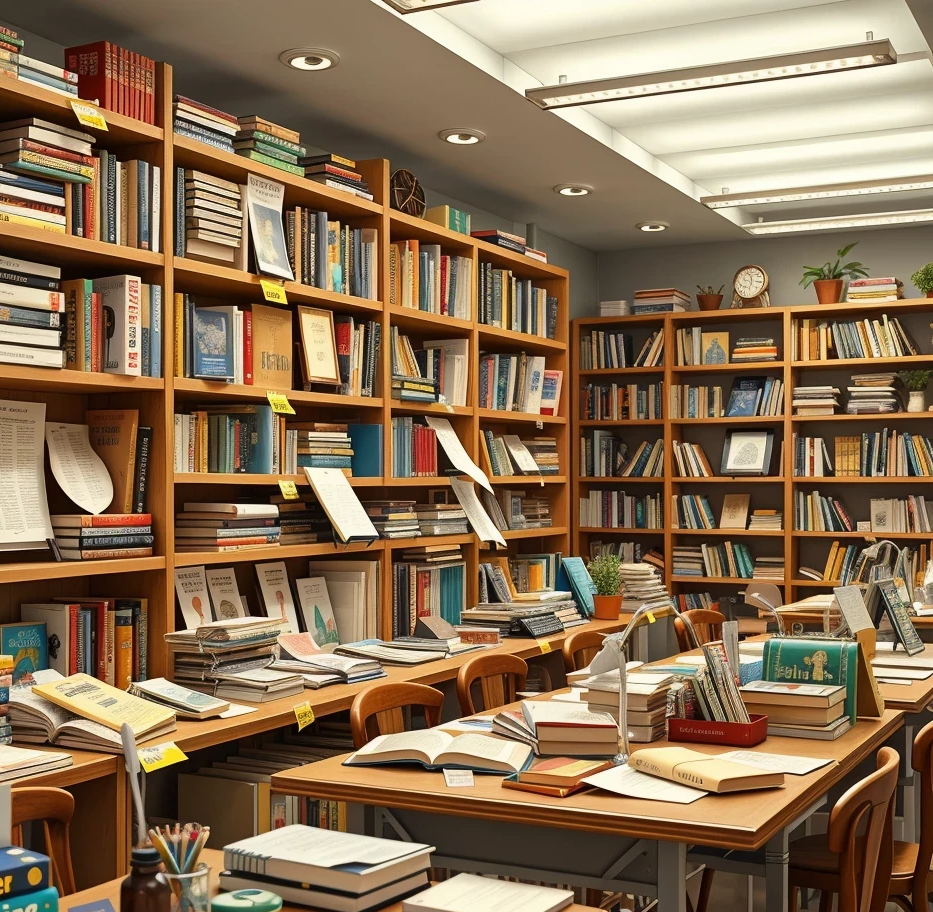HTM講座第13回 「数学の基本操作:集合の性質と扱い方を学ぶ」
今回はZFCを題材に、集合の基本操作や構成方法について学んでゆきます。
前回触れたように、ZFCは「破綻を避けるための基本ルール」です。
ルールは私たちを「不自由にする」ものではなく、「安全に自由に活動するための土台」というふうに考えてみてください。
ZFCは以下の2つから構成されます:
・ZF(ツェルメロ=フレンケル集合論)
・C(選択公理)
ZFに、Cが追加されてZFCという構成です。
◆ZFの基本的な考え方
ZFでは、「集合とは何か」をいちいち定義するのではなく、許される集合の操作・構成方法は何かをルール化するという方針をとります。
◆C(選択公理)の追加
「どんな集合も、各元が互いに素ならば、各元から元をひとつずつ取ってきたものもまた集合になる」という公理です。
・・・なぜ必要か?
・現代数学の証明に不可欠(認めることで、非常に重要なことが成り立つようになる)
しかし、「元が無限の集合から、ひとつずつ選択する」操作が可能であるという主張が「バナッハ=タルスキーのパラドックス」などの矛盾をもたらすことがあり、CはZFとは独立のものとして扱われます(だから、ZFCでは選択公理Cを明示的にZFに「追加」して使用しています)。
さて、ZFCには以下の10のルールがあります。それらのルールは、以下のように大まかに分類することができます。
【ZFCの公理の分類】
◆集合のありかた(性質)を制限するルール: 正則性公理・外延性公理(「おかしな集合」を排除し、整合性を保つためのルール)
◆集合の存在を保証するルール:空集合の公理
◆集合のつくりかたや操作に関するルール:対の公理・和集合の公理・べき集合の公理・分出公理・置換公理・選択公理・無限公理
ここではすべての公理についてひとつずつ細かく説明することはしません。
特に重要なものや基本的なものに絞って、集合の性質と扱い方を学びましょう。
まず、「分出公理」。
この公理は、ある集合が与えられたときに、その集合の元を自由に使って新しい集合を作れることを保証しています。
つまり、分出公理によって「部分集合」を作ることができます。
たとえば、集合X={a,b,c,d}の中から指定した条件p(x)を満たすb,cを選んで部分集合Aを作るとします。
A={x∈X | p(x)}={b,c}
次に、「順序対」をつくってみましょう。順序対はその名のとおり、順序を持ったペアのことです。
ただa と b という要素を集めて集合 {a, b} としただけでは、「どっちが先でどっちが後」という性質を持ちません。
しかし、数学において要素同士の「関係」や「関数」などを考えたいとき、“aからbへ(a→b)”というような順序を持たせたいという必要が出てきます。
そこで(a, b) の対を、 {{a}, {a, b}} (a ≠ b)と集合のかたちで表すことで、順序を規定するルールを作ります。
この定義により、
{{a}, {a, b}} ≠ {{b}, {b, a}} となり、a, bの順序を区別できるようになります。
このように、集合の操作だけで「順序」の概念が作れるのが面白いところです。
集合は「ただのものの集まり」ではないという予感がしてきましたか?
これはまだ序の口、次回はここから進めて、「関係」や「関数」を作ってみます。