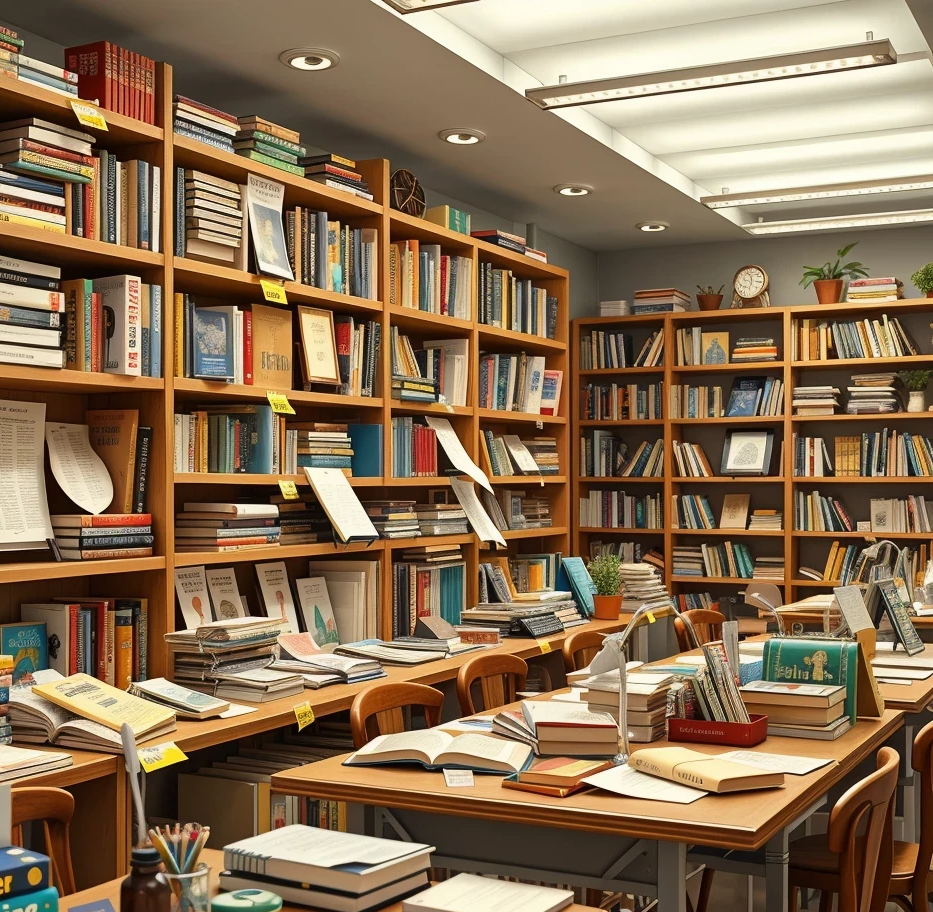
HTM講座第12回 「現代数学のルールブック」
前回、数学は記号を使って対象を記述する「言語のゲーム」だけど、書けるからといって「なんでも存在してOK」ということにはなりません、というお話をしました。
今回はその続きです。
「思いついた“集まり”はなんでも集合として扱っていい、という考え方」、これを「素朴集合論(Naive Set Theory)」と呼ぶことにしましょう。
これは「自然な直感」に従った考え方なので、最初に集合論を学ぶときには便利かもしれません。
しかし、「なんでも集めれば集合になる」という素朴な考えでは、いろいろな不都合が起こります。
たとえば、次の例について考えてみてください。
「自分で髭を剃らない男すべての髭を剃る床屋がいる。
では、この床屋自身の髭は誰が剃るのか?」
このような「自分自身を含まない集合の集合R」について、考えてみましょう。
このR自身はどうなるのか?R ∈ R ならば…
定義より、R ∉ R でなければならない(矛盾)
そして、R ∉ R ならば…
定義より、R ∈ R でなければならない(矛盾)
よって、「R ∈ R ⇔ R ∉ R」 という矛盾が生じる、という結果になります。
このような「自分自身を含まない集合の集合」を材料にして推論すると、破綻してしまうということです。
他にも破綻する例はあります。
それは、「全ての集合を集めた集合(全体集合)」です。
V = {x | x は全ての集合} とすると、これも矛盾を招きます。(全宇宙の中に全宇宙それ自身が含まれるような状態?)
・・・こういう集合を「考えてはいけない」というわけではないんですが、数学という巨大な建築物を構築しようとするなら、このような破綻を招く構造を礎にしては、いろいろまずい。
というわけで、「集合として扱っていいもの」に関する基本ルールを定める必要性が生じます。
◆集合(set)の基本ルール:
・集合とは、集合論の公理(※)に従いその「性質」を定められたものをいう
(※集合の在り方やつくりかたを定めたルールが複数あります)
・集合Aが集合Bに含まれるとき、AはBの元(要素)である、という
(集合もまた集合の要素たりえる、ということ。この定義があるために、現代数学に登場するすべてのものは集合として扱うことができます)
破綻を防ぐため、安全基準を満たしたルール、つまり集合についての「公理」を決めよう、という流れになります。
それで、 ツェルメロ=フレンケル集合論(ZFC) というものが、数学全体の土台を支えるルールブックとしての役割を担うことになります。
ZFCは現代数学の基本ルールですが、これだけが唯一絶対の土台というわけではなく、「連続体仮説」のように、ZFCでは証明も反証もできない命題も存在します。
しかし、少なくとも、次の役割を期待することができます。
【ZFCの役割】
・構造の破綻を避ける: ラッセル的なパラドックスを排除し、安全に設計可能
・公理に基づく構築: 全ての数学的対象(数・関数・空間など)を「集合」として定義可能
・共通言語: 現代数学のほぼ全てがZFCの枠内で形式化可能
・拡張と制限の指針: ZFCを基準に、「足りない」「強すぎる」を判断できる
数学を専門としないなら、ここまで厳密に考える必要はなく、素朴集合論で十分なんですが、なんとなく現代数学の「設計思想」のようなものをご理解いただけましたでしょうか?
次回、ZFCを題材に、集合の操作や構成方法について学んでゆきましょう。



