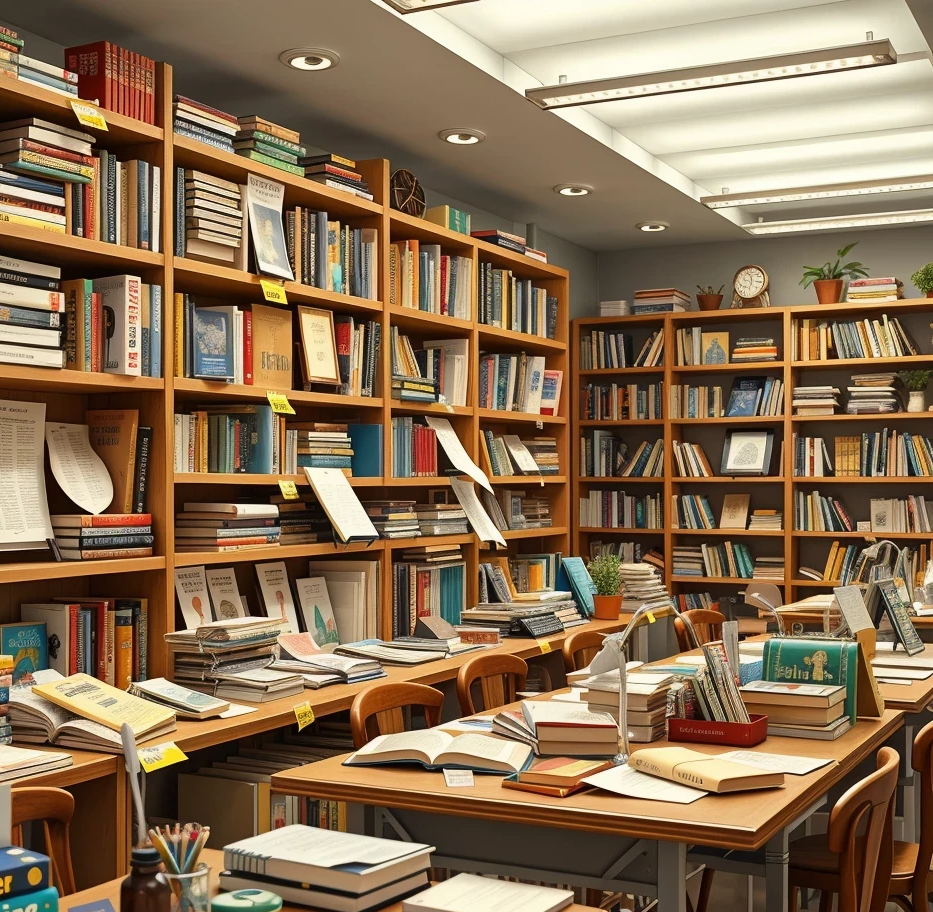HTM講座第11回 「存在のルール:集合論のお話」
今回から「集合論」の講義に移ります。
前回までで、「数学は想像以上に言語で記述される学問である」ということがおわかりになったかと思います。
しかし、その言語(=記号・公理・推論)と、記述対象(=“存在する”集合や数)には「ズレ」や「限界」がある、ということでもあります。
「この手紙は読まれない」と書かれた手紙を、今あなたが読んでいる。
・・・この命題は“真”か“偽”か?
言語的に記述できることと、それが“意味を持つ”か、“成立する”かは別問題なのです。
「書けばあるのか?」「定義すれば存在するといえるのか?」・・・さらに言えば「数学における“存在”とは何か?」というのが、今回のテーマです。
それに関連する興味深い話に「ラッセルのパラドックス」というものがあります。
・「自分自身を含まないすべての集合の集合」とは何か?
・それは存在するのか?
という問いです。
言語で“書ける”からといって、その対象が“存在する”とは限らない、ということですね。
(→記述の自由度 ≠ 存在の保証)
ですから、集合論の出発点として、「どんな集合でも考えていい」では破綻する、という可能性を考えねばなりません。
よって、「考えていい集合」と「考えてはいけない集合」を明確にするルール(=公理系)が必要だ、という流れになります。
もうひとつ、別の例でも考えてみましょう。
・・・「“赤いユニコーン”は存在するか?」
現実に存在するかどうかは置いといて、「赤いユニコーン」という言葉は使えるし、その姿や性質もイメージできる。
・・・でも「それが本当に存在する」と言えるのだろうか?
(→言語での記述可能性 ≠ 存在の証明)
「可測でない集合」「非構成的な実数」なども数学では定義できますが、「実体」として把握できるとは限りません。
・・・このような問いに答えるために、「何が存在してよいのか」を公理でルール付けする必要があります。
数学は、記号を使って対象を記述する「言語のゲーム」であるとも言えます。
しかし、書けるからといって、「なんでも存在してOK]ということにはなりません。
「どこまで“記述すればよい”のか?」
「何を“存在する”とみなしてよいのか?」
こうした問いに、ある種の“ルール”を与えるのが「集合論」です。
次回からは、この集合という“数学の素材”となる存在について、その基本性質と限界について探求していきましょう。