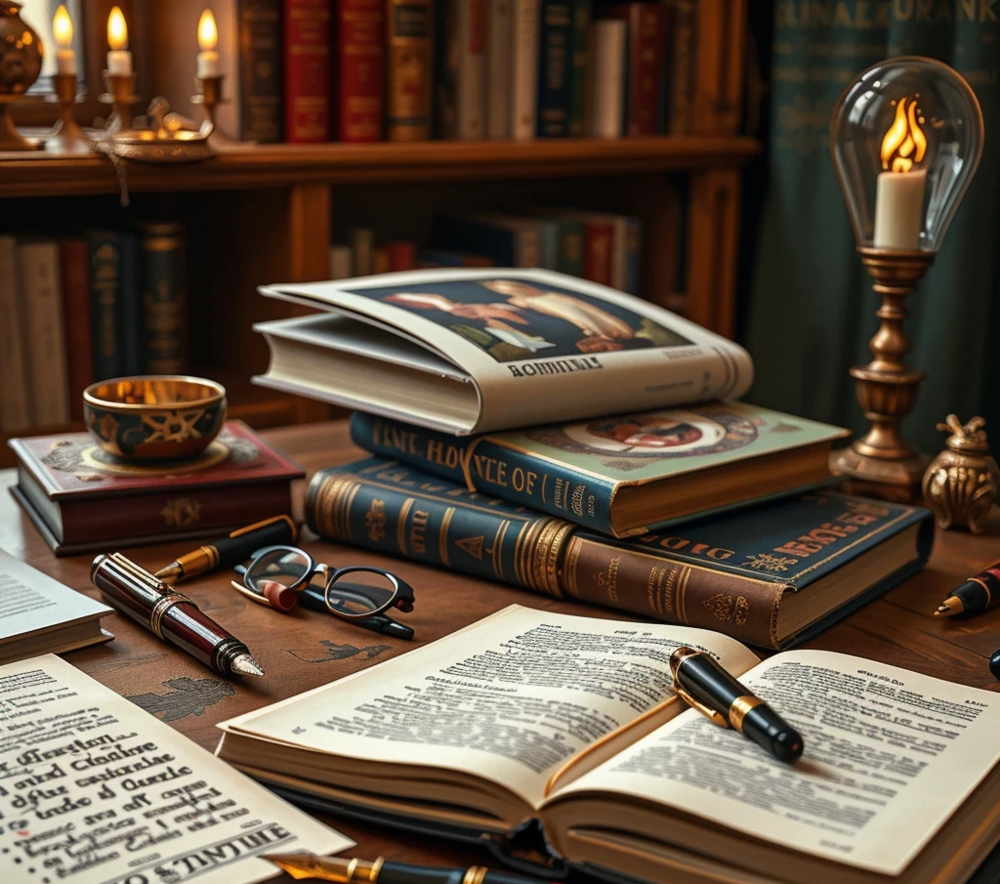HTM講座第10回 「鍵はあるけど全ての扉を開けられるわけではない」
前回は、一階述語論理の話から発展して、「モデル」についてのレクチャーでした。
今回は、数学を「体系」や「構造体」として見るだけでなく、それがなぜ成り立ち、どこまで拡張できて、どこに限界があるのか、という視点に立ち、「ゲーデルの不完全性定理」を題材に、数学の論理がどこまで世界を描けるか、という問いに迫ってみましょう。
一階述語論理は現代数学のほとんどの体系を表現するのに十分な強さを持っています。
◆一階述語論理で「表現可能」なこと:
自然数の公理化(ペアノ算術)
実数や有理数の公理化
群論・環論・体論などの代数体系
トポロジー
公理的集合論(ZFC)など
(※公理とは、証明を必要とせずに根拠として使用される基本的な真理のこと。一連の公理の集まりを「公理系」という)
これらはすべて一階述語論理の枠内で記述・形式化が可能で、現代の数学の99%は一階論理で「記述」できます。
◆しかし、「すべて」が可能ではない理由:
ゲーデルの不完全性定理(1931)により、「任意の無矛盾で十分に強い一階理論には、その理論内で証明も反証もできない命題が必ず存在する」ということが証明されました。
◆ヒルベルト・プログラム
19世紀末から20世紀初頭にかけ、数学の「集合」に関する矛盾が次々にみつかり、数学の基礎がゆらぐ「危機の時代」が訪れました。
その論争の中で、ヒルベルトは「形式主義」という、数学を形式的な記号列の操作としてとらえる立場から「ヒルベルト・プログラム」と呼ばれる計画を提唱します。
つまり、数学を「無矛盾ですべての真である命題を証明できる(つまり、証明できるもの = 真なるもの、という希望)」ものとして、完全で強固な論理の城を築こうとしたのです。
◆ゲーデルの不完全性定理
それに対する答えが、「ゲーデルの不完全性定理」です。不完全性定理は、次の2つの定理があります。
以下、簡単な説明です。
【第一不完全性定理】:「真だけど証明できない命題がある」
形式的な理論が「無矛盾で十分に強い」なら、必ずその理論内では証明できない“真”の命題がある。
➤ つまり、「形式的な証明」だけでは真理に到達できないこともある、ということ。
・・・たとえるなら、「地図の中に“この道は行き止まりです”と書かれていても、地図だけではそれが正しいかどうか確認できない」状態。
【第二不完全性定理】:「自分が矛盾していないことは、自分では証明できない」
「この論理体系は絶対に正しい」という保証を、その論理体系自身が出すことはできない。
➤ たとえばZFCやPAなどの各体系は、自分自身の「無矛盾性」を証明できない、ということ。
・・・「この本に“この本に書かれていることは全部正しい”と書いてある。でもそれ、誰が保証するの?」って話です。
◆一階述語論理の表現力の限界
結論として、一階述語論理で記述できても、すべての真理を一階述語論理で証明することは不可能ということです。
たとえば、「自然数全体の集合に適用される性質」のようなものを完全にとらえることができません。
「全ての部分集合を考える」といった集合論的に強い概念は、高階論理(2階以上)でないと表現できないことがあるのです。
◆高階論理(second-order logicなど)との比較:
高階論理はより強力な表現力を持ちます。(例:自然数全体を一意に定めるペアノ公理が書ける)
ただし、高階論理は完全性・コンパクト性など、一階論理の「美点」を失います。
◆数学はどこまで“真理”を語れるのか?
ゲーデルの不完全性定理により、数学体系の完全性は否定されました。
「数学は絶対ではない」ということが明らかになったわけですが、それは数学が破綻していて無意味だということではありません。
形式的操作(証明)は強力だが、それだけでは世界の全ては語れない、つまり真理と証明の間にあるギャップを明らかにしたことで、むしろ数学という知的ゲームの基盤が整った、とみることができます。
以上、数回にわたり、数理論理学の話題を取り上げ、数学的思考の骨格ともいえる、「証明とは何か」「数学的推論とは何か」という問題について、議論しました。
では、最後に、次の命題について考えてみてください。
「手紙に“この手紙は読まれない”と書いてある」
・・・この命題の真偽は?
次回より、「集合論」の講義に移ります。