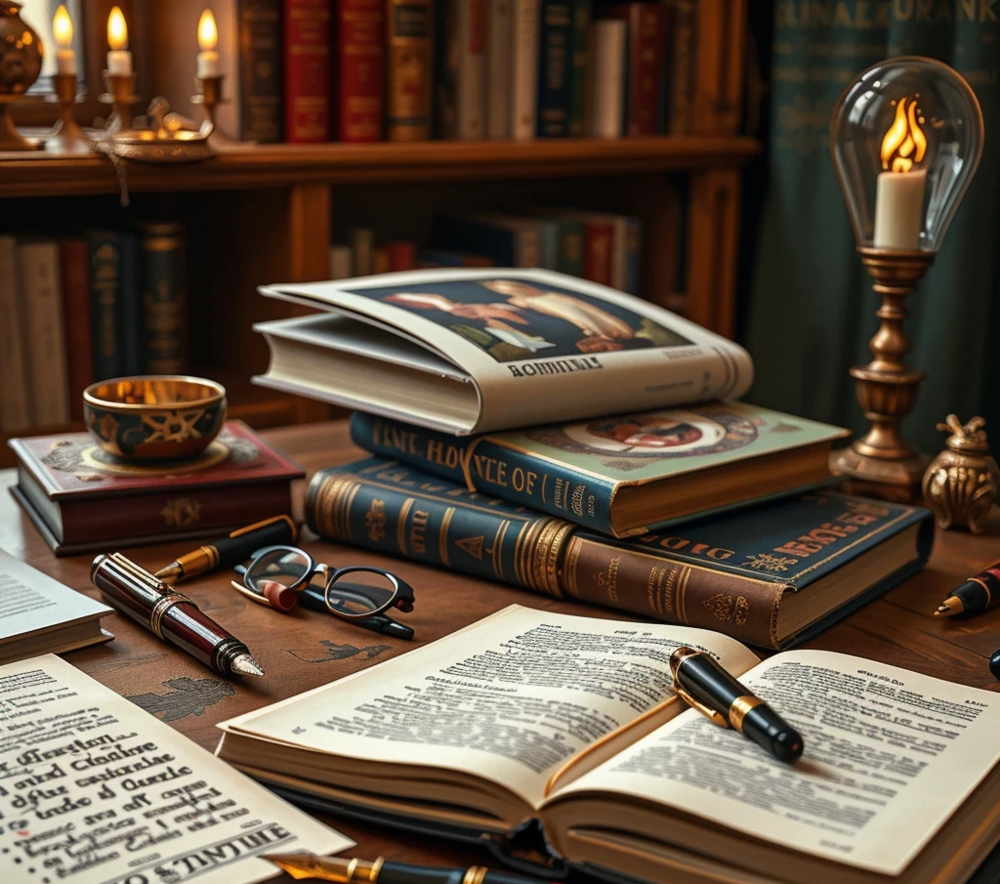
HTM講座第9回 「数学の世界の描き方:モデルのお話」
前回、「一階述語論理」についてお話ししました。
一階述語論理では、完全性・コンパクト性などの「きちんとした証明体系」があるため、ルールが明確で、機械的に筋道をたどることができて、機械的に“正しい”か“正しくない”かを判断できる、ということをお伝えしましたね。
ここで、その一階述語の「論理」にはどのような「性質」があるのか、もう少し詳しく説明します。
※一階述語の論理には、次のような性質があります。
・完全性 → 「理論にモデルがある ⇔ それを証明できる」(⇔ は「同値」(互いに必要十分条件))
・コンパクト性 → 「理論全体を見なくても、有限な部分だけで真かどうか判断できる」
・可算性 → 「どんなに大きな世界でも、小さく再現できる(モデルは縮小可能)」
ここに「モデル」という言葉が出てきました。一階述語の論理は、「モデル」という存在と直接つながっているんです。
数学における「モデル」は、「形式に意味を与える構造(宇宙)」であり、証明と解釈の橋渡しをする働きがあります。
なぜ、数学は一階で形式化するのがいいか、あらためて整理してみましょう。
理由1:形式的厳密さと完全性の恩恵を受けられる
一階述語論理では、「意味論的完全性」の意味で、完全です。
⇒証明できるものと真であるものが一致する、ということです。これにより、モデル理論的「意味」との対応ができます。
理由2:コンパクト性やローエンハイム=スコーレム(※)の定理も成立
⟹ つまり、有限的な推論やモデル理論の道具が豊富に使えるということです。
(※)ローエンハイム=スコーレムの定理(Löwenheim–Skolem theorem)は、
一階述語論理の「意味の世界(モデル)」について、とても興味深い・直感に反する性質を教えてくれる定理です。
◆定理の直感的な説明
「一階述語論理で記述された理論に、無限のモデル(解釈)が1つでもあるなら、“それより小さいサイズのモデル”も存在する」
特に重要なのはこれ:
「任意の無限モデルがあるなら、“可算モデル”も必ずある」
◆ 何が不思議なのか?
たとえば、集合論 ZFC(無限の集合を扱う強力な理論)を考えます。
ZFC は「実数の集合」や「すべての集合」など、“巨大で非可算”な対象を扱っています。
でもローエンハイム=スコーレムによると、ZFC も可算なモデルを持つ。
?つまり…
「非可算な集合が“存在する”という理論に、可算なモデルがある」・・・ってどういうこと!?ってことなんですが・・・
これは「スコーレムのパラドックス」として有名です。
モデルの“内側”では「これは非可算集合です」となっているのに、
モデルの“外から見る”と、そのモデル全体が「可算」である。
つまり、数学の“真偽”や“サイズ(大きさ)”は、モデルに依存することを示しています。
また、一階論理の体系は、可算な言語で記述できるため、形式的に扱いやすいということになります(数学の証明ではこの「形式的に扱えること」が極めて重要です)。
以上が、数学が一階で形式化するといい、ということの理由になります。
証明は、紙の上の形式的な作業、モデルは論理の「意味のある解釈」。
その両方がぴったり一致するというのが、一階述語論理のいいところです。
そして一階述語論理には、どんなに大きな世界も「もっと小さく解釈できる」という不思議な性質があります。
数学は完全な“唯一の世界”を描くものではなく、「たくさんの可能な世界(モデル)」を持ちうることを示しています。
これは数理論理学・モデル理論でとても重要な視点です。
ここまでで「論理の構造」と「数学が依拠している足場」が見えてきました。
次に向かうべきは、数学を「体系」や「構造体」として見るだけでなく、それがなぜ成り立ち、どこまで拡張できて、どこに限界があるのか、という視点です。
次回、有名な「ゲーデルの不完全性定理」を題材に、数学の論理がどこまで世界を描けるか、という問いに迫ってみましょう。



