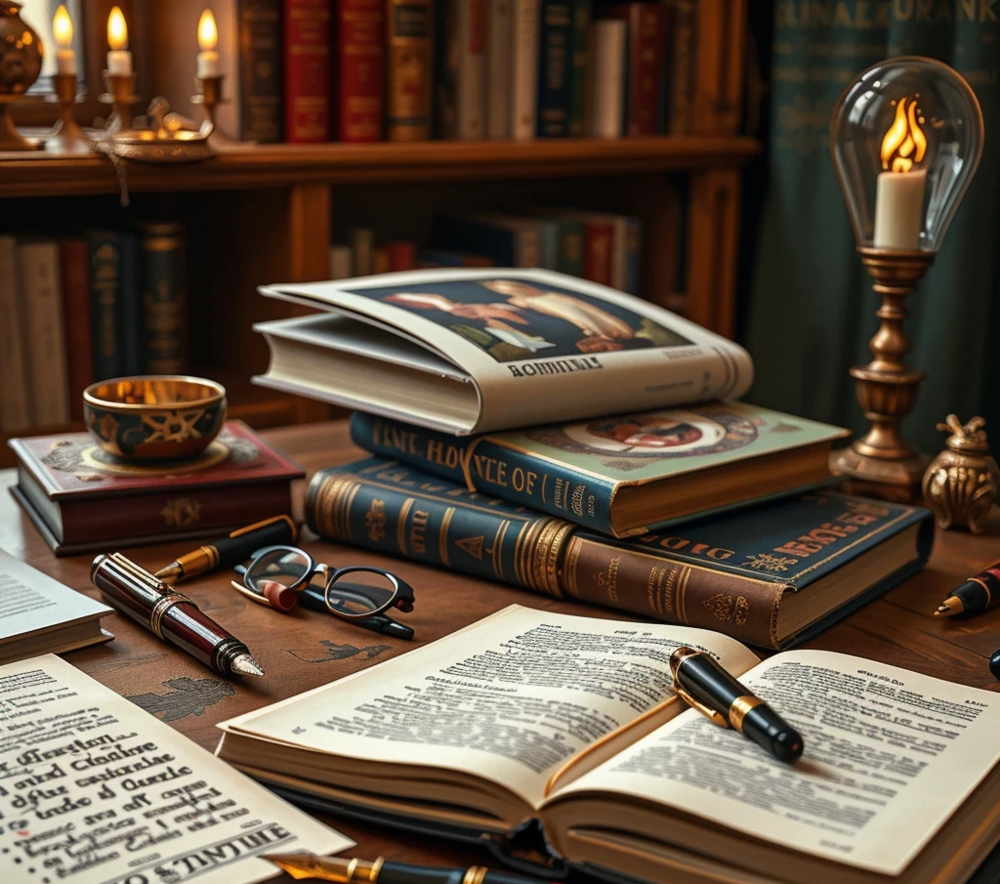HTM講座第8回「数学の言語で話せるようになるには」
第8回の講座をお届けします。
まず、前回の課題から。
【問】 以下の命題を命題論理/述語論理で記述し、何が見えるか比較しましょう。
命題: ある偶数は素数である
さて、命題論理では、P:ある偶数は素数である(ざくっと一文)
述語論理では、∃x (Even(x) ∧ Prime(x))・・・?
命題論理よりはなんとなく記号で対象をとらえられているような気もしますけど、Even(x)で偶数、Prime(x)で素数・・・これで満足できるでしょうか?
たとえば、偶数は「2で割り切れる」という定義でとらえたいときもあれば、文脈によっては「奇数ではない数」と定義したいケースもあるかもしれないですね。
もう少しきめ細やかな表現をするなら、
∃x∈N, (xmod2=0∧x>1∧∀a∈N, (a∣x→(a=1∨a=x)))
あたりでしょうか。
各部分の意味:
∃x∈N:自然数 x が存在する
xmod2=0:x は偶数である(2で割った余りが0)
x>1∧∀a∈N, (a∣x→(a=1∨a=x)):x は素数である
数学的推論は、「直観」や「意味」で動くのではなく、「構造」を記号で扱い、ルールに従って操作すること。これによって「前提から論理的に導けるかどうか」=証明の正しさを形式的に定めることができます。
つまり「数学的推論の骨格そのもの」を記述できるというわけです。
さて、「述語論理」なんですが、上で示した
∃x∈N, (xmod2=0∧x>1∧∀a∈N, (a∣x→(a=1∨a=x)))
のような形式は、正確には「一階述語論理」といいます。
一階述語論理は、
・変数(対象)(例:x, y)
・述語(性質、関係)(例:Man(x), Loves(x, y))
・量化子(全称 ∀、存在 ∃)
の要素から構成されるもので、「対象」「性質」「関係」「全体と一部」を正確に記述できます。
例:
「すべての人は死ぬ」→ ∀x (Person(x) → Mortal(x))
「ある猫は黒い」→ ∃x (Cat(x) ∧ Black(x))
ちなみに「一階」とは、“変数が個体(もの)について語るレベル”という意味です。変数が変数について語り始めると、それは「二階」の話になります。
一階では、変数が具体的な“もの”や“個体”を表します。
たとえば「チャチャは猫だ」は「Cat(Chacha)」、「すべての人は死ぬ」は「∀x (Person(x) → Mortal(x))」
ここで x は「人」や「猫」という“個体”を表しています。
じゃあ二階は?
「すべての対象には何らかの性質がある」みたいに、述語や性質そのものを変数として扱うレベルの話です。
つまり「変数が“述語や性質”について語る」のが二階です。
大まかにまとめると、
一階述語論理:
・「対象」「性質」「関係」「全体と一部」を正確に記述できる
・機械的に“正しい”か“正しくない”かを判断できる
二階述語論理:
・より豊かな表現ができる(たとえば「自然数全体」という性質そのものを語れる)
二階のほうが表現力が豊かなら、一階より二階がいい?
それはそんなに単純ではなく、二階では、
・不完全性(すべての真の命題が証明できるとは限らない)
・決定不能性(ある命題が真か偽かを判定する一般的な方法がない)
という問題が代わりに生じます。
一階述語論理は、しっかりしたルールが整っていて、どんな証明も“機械的にたどれる”ような、安心できる世界です。でも、二階になると話は一気に複雑になります。
つまり、“証明できるかどうか”を決めるルール自体が、はっきりしなくなってしまうんです。
一階では、完全性・コンパクト性などの「きちんとした証明体系」があるため、ルールが明確で、機械的に筋道をたどることができて、機械的に“正しい”か“正しくない”かを判断できる、という安全地帯が用意されています。
二階以上は、“より深いことが言える”かわりに、“何が正しいかを完全に判断できない”不確かな世界に入っていきます。
だから数学の土台は、まずこの“一階”のレベルでしっかり作ります。
そのため、現代数学の大体99%はこの「一階述語論理」という土台の上に構築されています。
(残りの1%は?という話はまた別の機会に)
「素数は無限に存在する」も、「ある偶数は素数である」も、自然言語で言えば単なる主張。でもそれを 一階述語論理の言葉で書けば、ルールに従って正しさを確かめたり、他の定理を導いたりすることができます。
「数学になる」=「主張が証明の網でつかまえらえる」ということ。それを可能にしているのが、「一階述語論理」です。
ですから、数学の言語で話せるようになるには、一階述語論理という土台の上に建てられた基本ロジックを習得する必要があります。
次回、一階述語論理の性質とその周辺についてもう少し掘り下げ、現代数学の構造とルールについて本質的な理解を深めましょう。