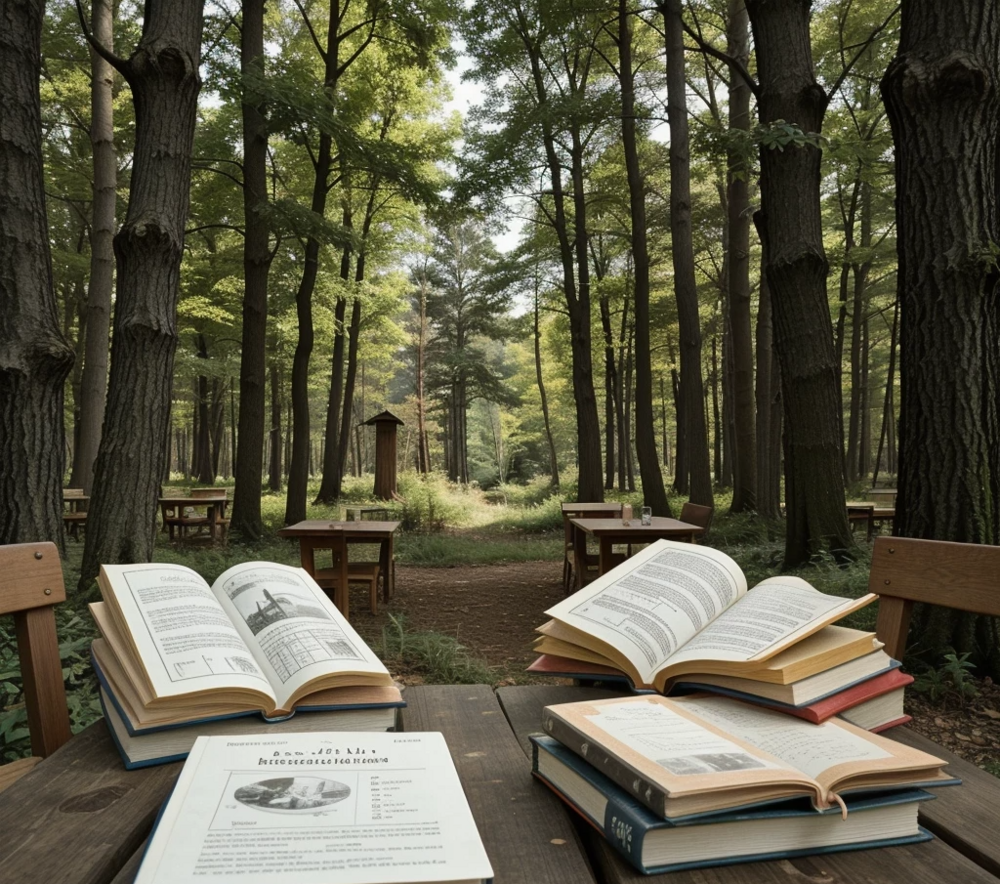
HTM講座第2回 「ロードマップを描く」
How to Think like a Mathematician-「HTM講座」の第2回です。
第1回は「エッセンスを取り出す&シンプルにする」というテーマで、数学的対象をどう扱って料理していくか、という感覚のイメージをつかんでいただきました。
さて、さっそく本格的なレクチャーに入っていきたいところですが、その前に今回は講座全体のロードマップ-〈目標達成までのプロセス〉を確認したいと思います。
大学数学のカリキュラムでは、高校数学との接続がイメージしやすい「線形代数」「微積分」、数学の基本となる「論理と集合」から導入するケースが一般的かと思いますが、
HTM講座では、まず
「①数理論理学」からはじめます。
数理論理学は数学的思考の骨格ともいえる、「証明とは何か」「数学的推論とは何か」という問題について、厳密に議論します。ここでまず、公理系、定義、定理、命題、推論規則など、「数学的に考える」ための土台作りに必要な内容を、しっかり理解します。
次に
「②集合論」を学びます。
数学には、代数系・幾何系・解析系とそのサブジャンルというふうに様々な分野がありますが、数学というのはどの分野であっても「集合」と「写像」という概念が根底にあります。ですから、各分野に進む前に、基本となる「集合論」を押さえておきます。
その次は
「③圏論」です。
圏論は数学の「空間」を統一的に眺めるためのモノの見方です。
多くの数学の分野がそれぞれ「対象となる空間」とそれらの空間の間をつなぐ「写像」によって構成されています。この考え方を明確に定義するのが「圏論」です。また、圏論は集合論との対比によって学ぶと効果的です。
※現代数学では、「集合論的な見方」と「圏論的な見方」の両方を押さえておくことが大切です。
次にようやく、数学の三大分野である、代数・幾何・解析の各分野に進みます。
①~③で学んだことを土台にして、まず〈代数系〉です。
「演算を持つ集合」である〈代数系〉の基本と、ベクトル空間における線形写像を扱う「線形代数」、「群論基礎」などを取り上げる予定です(群論でも「空間」と「写像」という概念が基本にあります)。
つづけて、〈幾何系〉で、
「位相空間論」でトポロジー的、「微分幾何学」で微分構造的な性質を持つ空間と作用について学び、
さらに
〈解析系〉で変化を記述するモデルとしての「微積分」、
と順に取り上げる予定です。
※ちなみに、代数系や幾何系での「写像」は、「空間の構造を保つ作用」を持つもの、という意味合いがありますが、解析系における「写像」は、それに加えて「連続性」「極限」「収束」といった性質を保つもの、という意味もあります。
以上、数学世界の各分野の本質的なつながりを考えて、HTM講座のロードマップを描いてみました。
HTM講座では各分野を詳しく説明、網羅することが目的ではなく、「数学者のように考える」センス、感覚を習得するために必要な勘どころを押さえることを目指します。
少しずつでも力がついていることを実感できるようなレクチャーを提供したいと思います。
次回からの講義をお楽しみに!



