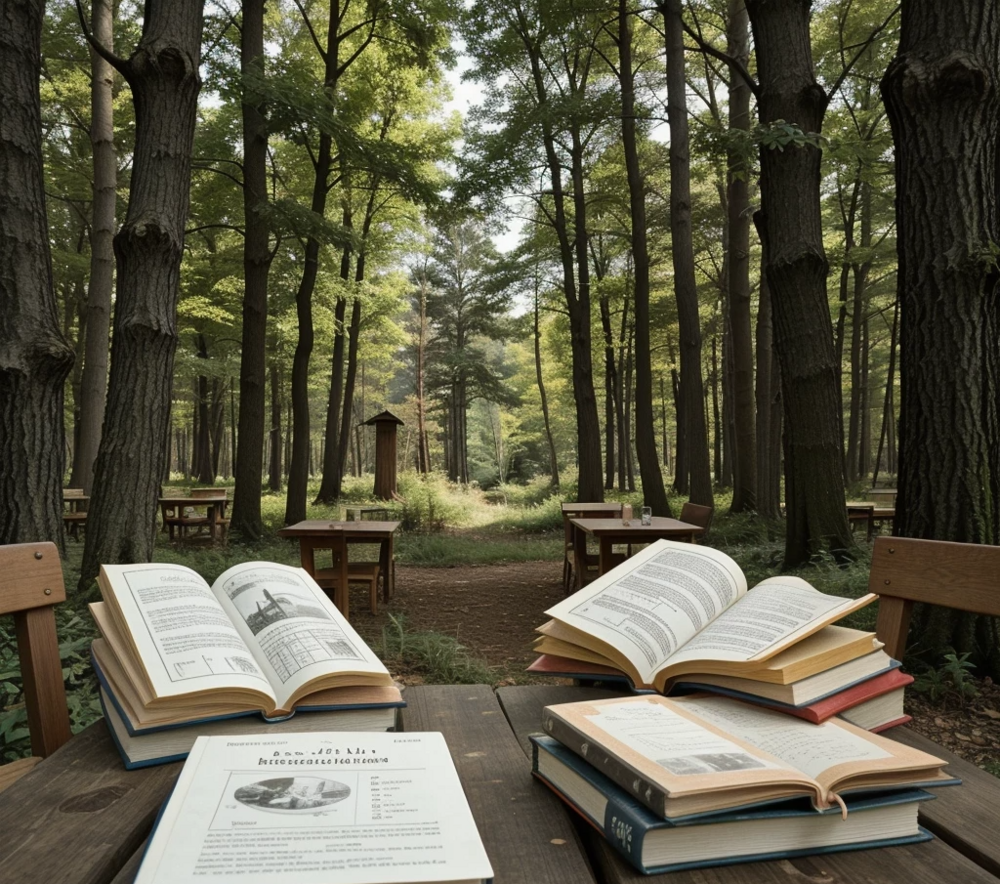HTM講座第3回 「推論のかたち」
How to Think like a Mathematician-「HTM講座」の第3回です。
前回は、ガイダンスとして、講座全体のロードマップ-〈目標達成までのプロセス〉を確認しました。
今回から本格的な講義に入りますが、「数理論理学」の本題に入る前に、この問題を解いてみてください。
【問題】
4枚のカードが、テーブルに置かれている。
それぞれのカードの片面には数字が書かれていて、その裏面には色が塗られている。
今、奇数(3)・偶数(8)・青の面・赤の面が見えている状態である。
このとき、「カードの片面に偶数が書かれているならば、その裏面は赤く塗られている」というルールになっていることを確かめるために、ひっくり返す必要があるカードはどれか?
最低限の枚数で、ルールが守られているかどうかを確かめてほしい。
(反転させる必要がないカードを反転させるか、反転させる必要があるカードを反転しない場合、課題に失敗したとみなされます)
・・・さて、答えは出ましたでしょうか?
正解は、「偶数(8)のカード」と「青(赤ではない)カード」をひっくり返す、です。
・・・いかがでしょう。ルールが守られているかどうかを検証するために、最低限調べなければならない要素を推論する問題でした。
では、この問題をこのように変えるとどうでしょう?
4人の人物が、飲み物を飲んでいる。
それぞれ、
・18歳で何を飲んでいるか不明
・22歳で何を飲んでいるか不明
・年齢不明でオレンジジュースを飲んでいる
・年齢不明でビールを飲んでいる
さて、「アルコール飲料を飲んでいる人は20歳以上でなければならない」というルールが守られているかどうかを検証するために、最低限調べなければならない人物は誰か?
・・・どうでしょう?・・・この問いに悩む方はまずいらっしゃらないかと思いますが、先に挙げたカードの問題と構造が同じであることに気づかれましたか?
これは心理学者ウェイソンの考案した論理問題で、正答率が非常に低いことが知られています。
私たちが日常生活で出会う推論ルールは、どちらかというと厳密な論理学に基づいたものというより、社会経験を通じて自然に学んだものです。
人間の「推論」は「文脈」に依存する傾向がある・・・というわけで、今回は「推論のかたち」というテーマでお話させていただきました。
社会的文脈から離れた記号を要素として取り入れただけで、人間にとって扱いづらい問題になってしまいます。
「具体」と「抽象」という2つの層の違いを意識して、必要に応じてその間を行き来できる人がどれほどいるでしょうか・・・
そういったこともふまえながら、次回より「数理論理学」という分野を学んでいきます。